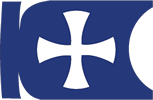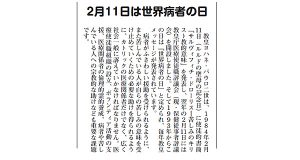「宣教地召命促進の日」を呼びかける教皇庁使徒聖ペトロ事業の目的は、すべてのキリスト者が宣教地の地元の司祭と神学生、男女修道者と志願者を育てる必要性を意識し、物的援助だけでなく、祈りと信仰生活による支援を促進していくことです。
この日、わたしたちはとくに祈りと犠牲によって、「収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に」願います。
当日の献金はローマ教皇庁・福音宣教省に集められ、全世界の宣教地の司祭養成のために用いられます。
教区本部事務局では年末年始休業を12月29日(月)〜1月4日(日)とさせていただきます。ご了承下さい。
平和のために祈りましょう
聖パウロ6世教皇は1967年12月8日、ベトナム戦争が激化するなか、来たる1月1日を平和の日とし、平和のために特別な祈りをささげるよう呼びかけました。それ以来、全世界のカトリック教会は毎年1月1日を「世界平和の日」とし、戦争や分裂のない平和な世界が来るように祈っています。
平和はキリスト教そのものに深く根ざしています。キリスト者にとって平和を唱えることは、キリストを告げ知らせることにほかなりません。新年にあたって「信仰の原点に立ち戻り、すべての善意ある人々と手をたずさえて、平和な世界の実現に向かって、カトリック信者としての責任を果たしていく」(日本司教団『平和への決意』)ことができるよう決意を新たにしたいと思います。
ライブ配信のお知らせ
カテドラルでの中野司教のミサをライブ配信いたします。
聖ヨハネ・パウロ二世教皇は、1984年2月11日(ルルドの聖母の記念日)に使徒的書簡「サルヴィフィチ・ドローリス︱苦しみのキリスト教的意味」を発表し、翌年の同日に教皇庁医療使徒職委員会(後に保健従事者評議会となり、現在は総合人間開発省に統合)を開設しました。そして1993年からこの日は「世界病者の日」と定められ、毎年教皇メッセージが発表されています。
病者がふさわしい援助を受けられるように、また苦しんでいる人が自らの苦しみの意味を受け止めていくための必要な助けを得られるように、カトリックの医療関係者に対してだけではなく、広く社会一般に訴えていかなければなりません。医療使徒職組織の設立、ボランティア活動の支援、医療関係者の倫理的霊的養成、病者や苦しんでいる人への宗教的な助けなども重要な課題です。
世界病者の日教皇メッセージ一覧(カトリック中央協議会のサイト)
1981年、聖ヨハネ・パウロ2世教皇は広島で、「過去を振り返ることは、将来に対する責任を担うことである」と述べられました。
戦争を振り返り、平和を思うとき、平和は単なる願望ではなく、具体的な行動でなければなりません。そこで日本のカトリック教会は、その翌年、もっとも身近で忘れることのできない、広島や長崎の事実を思い起こすのに適した8月6日から15日までの10日間を「日本カトリック平和旬間」と定めました。
「平和旬間」に広島教区と長崎教区では、全国から司教をはじめとして多くの信者が集まり、「平和祈願ミサ」がささげられます。
各教区でも、平和祈願ミサや平和行進、平和を主題とした映画会、講演会、研修会、平和を求める署名などが行われます。
「平和を紡ぐ旅 -希望を携えて-」
戦後80年司教団メッセージ平和を望むすべての皆様、若者の皆様へ
はじめに
今年、わたしたちは戦後80年を迎えました。この節目の年にあたり、あらためていのちを奪われた人々、さまざまなかたちで尊厳を侵害された人々、また破壊された自然環境を心に留め、祈りをささげます。人の生涯と同じほどの年月を経て、わたしたちは今、人間の尊厳を大切にするのだという思いを、平和を実現しようという願いを、どのように次の世代へと受け渡していくのでしょうか。25年に一度カトリック教会で祝われる聖年を迎えた今年、平和な世界を造る希望をもって皆様と、とくに若者の皆様と、ともに歩みを進めていきたいと願っています。戦後80年を経て
2024年10月に日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞しました。「核兵器は極めて非人道的な殺りく兵器であり人類とは共存させてはならない、すみやかに廃絶しなければならない」。受賞に際し行った演説で代表委員の田中熙巳氏が語ったことばは世界の人々の心に届き、核廃絶について考えるきっかけとなったことでしょう。そのことばには、80年にわたって語り続けてこられた重みがありました。あの戦争を経験した多くの人が、日本でも、世界でも、80年の間その経験を語り伝え、平和のために行動してこられたのです。
80年が経過した今、実際に戦争を経験した人は非常に少なくなってきています。だからこそ、わたしたちは歴史的事実に誠実に向き合い、学び、記憶にとどめ、次世代に伝え、平和のために生かしていかなければなりません。教皇フランシスコは2019年広島にて次のようにいわれました。「思い出し、ともに歩み、守る。この三つは倫理的命令です。これらは、まさにここ広島において、よりいっそう強く、より普遍的な意味をもちます。この三つには、平和となる道を切り開く力があります。ですから、現在と将来の世代に、ここで起きた出来事の記憶を失わせてはなりません」。
この意味で、若者の皆様が広島や長崎、そして沖縄に、巡礼や平和学習の旅をなさるのはとても大切な、意義のあることです。
わたしたちはアジア・太平洋戦争以前から、日清・日露戦争や植民地支配を含むさまざまな行為によって、日本が近隣諸国に対し多大な苦しみを与えてきたことを忘れてはなりません。80年前、戦争終結に至る歴史の流れの中で、カトリック教会が平和の実現に求められる役割を十分に果たせなかった側面があります。明治以降、日本国が天皇を中心とした国家体制を整える中で、カトリック教会は忠君愛国の姿勢を示そうと苦心しました。その過程で、正戦論を用いて日本の戦争を正当化し、支持する立場を取ったのです。こうした過去を真摯に受け止め、回心し、次世代を担う人々とともに平和への歩みを進めていきたいと思います。世界の今
多くの市民による80年間の平和を目指す取り組みに並行して、国際連合とその加盟国は歩みを続けてきました。しかし平和を希求する国連憲章その他さまざまな規範は都合よく解釈され、また無視されることによって、世界は今、非道な戦争を目の当たりにしています。ウクライナとロシア、パレスチナとイスラエルをはじめとする中東、またミャンマーやアフリカ諸国でも、日々、多くの人が殺され、目を覆いたくなる惨状が続いています。戦争は、人道的介入、予防、防衛などを建前にし、正義の名のもとに行われます。しかしそれらは自らを正当化するための拡大解釈であって、その結果多くの民間人が被害に遭い、環境が破壊され、さまざまなリスクが拡大するのです(回勅『兄弟の皆さん』258参照)。さらに、実際に戦闘行為を行っている国以外にも、戦争にならないように、また戦争になったときのためにと、軍備を強化する国が増えています。日本も同じで、日本国憲法9条により従来「できない」とされてきた集団的自衛権の行使容認、他国領土を攻撃できる長射程ミサイルの配備や武器輸出の解禁、自衛隊基地の新設、防衛費の大幅増など、国是としてきた平和主義がかすんでいます。
沖縄島をはじめ南西諸島においては、「防衛」の名のもと、次々とミサイル部隊が配備されています。80年前の沖縄戦では、9万4千人余りの一般住民を含む、20万を超える人のいのちが奪われました。沖縄の人々は、その恐ろしい戦争の記憶、そして戦後の米軍基地に関連するさまざまな暴力事件に苦しみながらも、あくまで非暴力による平和アピールを続けています。戦争を二度と繰り返さないように、性暴力を含む基地由来の被害が二度と起こらないように、そう叫び続けているにもかかわらず、今また、ミサイル基地等が目の前に作られているのです。沖縄の年配のかたがたの間には、「戦争の準備をしている」「戦争前と同じ歩みをしている」、そうした声が聞かれます。
戦争そのものの恐ろしさ、罪深さは、多くの人にとって明らかですが、戦争へと人々を導いた日常における思想や価値観の植えつけが、知らぬ間に世論を戦争に向けて突き進むものへと変えていくことを、80年前の経験から学ばねばなりません。今の日本は、果たして平和への道を進んでいるのでしょうか。
核兵器の廃絶に向けて
教皇フランシスコは2019年広島で「確信をもって、あらためて申し上げます。戦争のために原子力を使用することは、現代においては、これまで以上に犯罪とされます。人類とその尊厳に反するだけでなく、わたしたちの共通の家の未来におけるあらゆる可能性に反する犯罪です。原子力の戦争目的の使用は、倫理に反します。核兵器の所有は、それ自体が倫理に反しています」といわれました。
日本被団協のノーベル平和賞受賞は、世界が核兵器使用の脅威の中で「核抑止」から抜け出し、核兵器廃絶に向かうための大きな一歩です。核兵器は、爆発時だけでなく、その後の長い時間にわたる健康被害や社会的差別、そして環境破壊を引き起こすことを、被爆国に生きるわたしたちは経験してきました。日本の司教団は戦後50年にあたって、強い決意のうちに宣言しました。
「核兵器の破壊的な力を体験したわたしたちには、その貴重な証人として、核兵器の廃絶を訴え続けていかなければならない責任があります」(「平和への決意 戦後五十年にあたって」)。核兵器廃絶に向けた取り組みは、広島・長崎と米国の司教たちとのパートナーシップによるネットワークなどにおいて広がりを見せています。今回の受賞が、核兵器のない世界に向けた希望の灯となるように祈るとともに、世界と日本政府がこの「時のしるし」を深く心に留め、一刻も早く核兵器禁止条約の署名・批准に向けて行動することを強く求めます。
真の平和とは
聖書が語る「平和(シャローム)」は、もともと「欠けたところのない状態」という意味をもつことばです。その意味で、平和は、単に戦争や争いがない状態なのではなく、この世界が神の前に欠けるところのない状態、すなわち神がきわめてよいものとして造られたこの世界のすべてが、それぞれ尊重され、調和のうちにある状態のことだといえるでしょう。ですから、平和のために働こうとするとき、わたしたち自身の神との関係、人々との関係、自然環境との関係を振り返り、神の前に望ましい関係であろうと回心し、対話することなしには前に進めません。平和とは、核兵器や武力の均衡によってもたらされるものではないのです。希望をともにして歩む
今年、カトリック教会は聖年を祝っています。これは、旧約聖書のレビ記(25章10節参照)にある「ヨベルの年」にちなんだ行事です。レビ記によるとこの年は、畑を休ませ、貧困などの理由により売却を余儀なくされた土地が返却され、雇い人となった同胞が解放され、負債が免除されたりする解放の年で、50年に一度巡ってきます。カトリック教会では、25年に一度聖年を実施し、神の前にすべての人が尊い存在であることを再確認し、権利を侵害されているならばその状態を解消し、搾取されているならばそれを返済し、負債から解放されるよう働きかけています。まさに、欠けてしまった状態から、本来の状態に戻す、平和を実現するための年といえるでしょう。前教皇フランシスコは、今年の聖年のテーマを「希望の巡礼者」とし、「聖年が、すべての人にとって、希望を取り戻す機会となりますように」と招いています。
また、新教皇レオ十四世は最初の祝福の際、「あなたがたに平和があるように……。この平和のあいさつが皆さんの心に入りますように。皆さんの家庭に、どこにいたとしてもすべての人に、すべての民族に、すべての地に届きますように。あなたがたに平和があるように」と呼びかけられました。
平和を望むすべての皆様、若者の皆様、この80年の間、幾世代にもわたって受け継がれてきた平和への歩みを自らのものとし、希望を携え、平和を紡ぐ旅をともに歩み続けてまいりましょう。
教皇フランシスコは2019年に「すべてのいのちを守るため」をテーマとして来日し、多くのメッセージを残してくださいました。これにこたえ、実際的な行動を呼びかけるために制定されたのがこの月間です。
9月1日(正教会における「被造物の保護を祈る日」)から10月4日(アシジの聖フランシスコの記念日)という期間は、元は2007年の第3回ヨーロッパエキュメニカル会議が「被造物のための期間」として提唱し、世界教会会議によって支持されたものです。被造物を大切にする世界祈願日の制定を知らせる書簡において教皇は、この世界教会会議との同調を願っています。
すべての人が手を取り合わなければ、すべてのいのちは守れません。ですから、エキュメニカルな視
点も諸宗教との協力も、ともに不可欠なのです。
2021年 すべてのいのちを守るための月間
日本カトリック司教協議会会長談話
「神の住まい、地球共同体を一新しよう」
「すべてのいのちを守るための月間」は、教皇のご意向によって2020年から実施されるはずでしたが、新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。今年は、教皇庁人間開発のための部署が発表したテーマ ―「皆のための家?神の住まいを一新する。」― をほぼそのまま紹介して会長談話とさせていただき、全教会と歩みを共にできたらと思います。>>>続きを読む
平和のために祈りましょう
聖パウロ6世教皇は1967年12月8日、ベトナム戦争が激化するなか、来たる1月1日を平和の日とし、平和のために特別な祈りをささげるよう呼びかけました。それ以来、全世界のカトリック教会は毎年1月1日を「世界平和の日」とし、戦争や分裂のない平和な世界が来るように祈っています。
平和はキリスト教そのものに深く根ざしています。キリスト者にとって平和を唱えることは、キリストを告げ知らせることにほかなりません。新年にあたって「信仰の原点に立ち戻り、すべての善意ある人々と手をたずさえて、平和な世界の実現に向かって、カトリック信者としての責任を果たしていく」(日本司教団『平和への決意』)ことができるよう決意を新たにしたいと思います。
ライブ配信のお知らせ
カテドラルでの中野司教のミサをライブ配信いたします。
聖ヨハネ・パウロ二世教皇は、1984年2月11日(ルルドの聖母の記念日)に使徒的書簡「サルヴィフィチ・ドローリス︱苦しみのキリスト教的意味」を発表し、翌年の同日に教皇庁医療使徒職委員会(後に保健従事者評議会となり、現在は総合人間開発省に統合)を開設しました。そして1993年からこの日は「世界病者の日」と定められ、毎年教皇メッセージが発表されています。
病者がふさわしい援助を受けられるように、また苦しんでいる人が自らの苦しみの意味を受け止めていくための必要な助けを得られるように、カトリックの医療関係者に対してだけではなく、広く社会一般に訴えていかなければなりません。医療使徒職組織の設立、ボランティア活動の支援、医療関係者の倫理的霊的養成、病者や苦しんでいる人への宗教的な助けなども重要な課題です。
世界病者の日教皇メッセージ一覧(カトリック中央協議会のサイト)
1981年、聖ヨハネ・パウロ2世教皇は広島で、「過去を振り返ることは、将来に対する責任を担うことである」と述べられました。
戦争を振り返り、平和を思うとき、平和は単なる願望ではなく、具体的な行動でなければなりません。そこで日本のカトリック教会は、その翌年、もっとも身近で忘れることのできない、広島や長崎の事実を思い起こすのに適した8月6日から15日までの10日間を「日本カトリック平和旬間」と定めました。
「平和旬間」に広島教区と長崎教区では、全国から司教をはじめとして多くの信者が集まり、「平和祈願ミサ」がささげられます。
各教区でも、平和祈願ミサや平和行進、平和を主題とした映画会、講演会、研修会、平和を求める署名などが行われます。
「平和を紡ぐ旅 -希望を携えて-」
戦後80年司教団メッセージ平和を望むすべての皆様、若者の皆様へ
はじめに
今年、わたしたちは戦後80年を迎えました。この節目の年にあたり、あらためていのちを奪われた人々、さまざまなかたちで尊厳を侵害された人々、また破壊された自然環境を心に留め、祈りをささげます。人の生涯と同じほどの年月を経て、わたしたちは今、人間の尊厳を大切にするのだという思いを、平和を実現しようという願いを、どのように次の世代へと受け渡していくのでしょうか。25年に一度カトリック教会で祝われる聖年を迎えた今年、平和な世界を造る希望をもって皆様と、とくに若者の皆様と、ともに歩みを進めていきたいと願っています。戦後80年を経て
2024年10月に日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞しました。「核兵器は極めて非人道的な殺りく兵器であり人類とは共存させてはならない、すみやかに廃絶しなければならない」。受賞に際し行った演説で代表委員の田中熙巳氏が語ったことばは世界の人々の心に届き、核廃絶について考えるきっかけとなったことでしょう。そのことばには、80年にわたって語り続けてこられた重みがありました。あの戦争を経験した多くの人が、日本でも、世界でも、80年の間その経験を語り伝え、平和のために行動してこられたのです。
80年が経過した今、実際に戦争を経験した人は非常に少なくなってきています。だからこそ、わたしたちは歴史的事実に誠実に向き合い、学び、記憶にとどめ、次世代に伝え、平和のために生かしていかなければなりません。教皇フランシスコは2019年広島にて次のようにいわれました。「思い出し、ともに歩み、守る。この三つは倫理的命令です。これらは、まさにここ広島において、よりいっそう強く、より普遍的な意味をもちます。この三つには、平和となる道を切り開く力があります。ですから、現在と将来の世代に、ここで起きた出来事の記憶を失わせてはなりません」。
この意味で、若者の皆様が広島や長崎、そして沖縄に、巡礼や平和学習の旅をなさるのはとても大切な、意義のあることです。
わたしたちはアジア・太平洋戦争以前から、日清・日露戦争や植民地支配を含むさまざまな行為によって、日本が近隣諸国に対し多大な苦しみを与えてきたことを忘れてはなりません。80年前、戦争終結に至る歴史の流れの中で、カトリック教会が平和の実現に求められる役割を十分に果たせなかった側面があります。明治以降、日本国が天皇を中心とした国家体制を整える中で、カトリック教会は忠君愛国の姿勢を示そうと苦心しました。その過程で、正戦論を用いて日本の戦争を正当化し、支持する立場を取ったのです。こうした過去を真摯に受け止め、回心し、次世代を担う人々とともに平和への歩みを進めていきたいと思います。世界の今
多くの市民による80年間の平和を目指す取り組みに並行して、国際連合とその加盟国は歩みを続けてきました。しかし平和を希求する国連憲章その他さまざまな規範は都合よく解釈され、また無視されることによって、世界は今、非道な戦争を目の当たりにしています。ウクライナとロシア、パレスチナとイスラエルをはじめとする中東、またミャンマーやアフリカ諸国でも、日々、多くの人が殺され、目を覆いたくなる惨状が続いています。戦争は、人道的介入、予防、防衛などを建前にし、正義の名のもとに行われます。しかしそれらは自らを正当化するための拡大解釈であって、その結果多くの民間人が被害に遭い、環境が破壊され、さまざまなリスクが拡大するのです(回勅『兄弟の皆さん』258参照)。さらに、実際に戦闘行為を行っている国以外にも、戦争にならないように、また戦争になったときのためにと、軍備を強化する国が増えています。日本も同じで、日本国憲法9条により従来「できない」とされてきた集団的自衛権の行使容認、他国領土を攻撃できる長射程ミサイルの配備や武器輸出の解禁、自衛隊基地の新設、防衛費の大幅増など、国是としてきた平和主義がかすんでいます。
沖縄島をはじめ南西諸島においては、「防衛」の名のもと、次々とミサイル部隊が配備されています。80年前の沖縄戦では、9万4千人余りの一般住民を含む、20万を超える人のいのちが奪われました。沖縄の人々は、その恐ろしい戦争の記憶、そして戦後の米軍基地に関連するさまざまな暴力事件に苦しみながらも、あくまで非暴力による平和アピールを続けています。戦争を二度と繰り返さないように、性暴力を含む基地由来の被害が二度と起こらないように、そう叫び続けているにもかかわらず、今また、ミサイル基地等が目の前に作られているのです。沖縄の年配のかたがたの間には、「戦争の準備をしている」「戦争前と同じ歩みをしている」、そうした声が聞かれます。
戦争そのものの恐ろしさ、罪深さは、多くの人にとって明らかですが、戦争へと人々を導いた日常における思想や価値観の植えつけが、知らぬ間に世論を戦争に向けて突き進むものへと変えていくことを、80年前の経験から学ばねばなりません。今の日本は、果たして平和への道を進んでいるのでしょうか。
核兵器の廃絶に向けて
教皇フランシスコは2019年広島で「確信をもって、あらためて申し上げます。戦争のために原子力を使用することは、現代においては、これまで以上に犯罪とされます。人類とその尊厳に反するだけでなく、わたしたちの共通の家の未来におけるあらゆる可能性に反する犯罪です。原子力の戦争目的の使用は、倫理に反します。核兵器の所有は、それ自体が倫理に反しています」といわれました。
日本被団協のノーベル平和賞受賞は、世界が核兵器使用の脅威の中で「核抑止」から抜け出し、核兵器廃絶に向かうための大きな一歩です。核兵器は、爆発時だけでなく、その後の長い時間にわたる健康被害や社会的差別、そして環境破壊を引き起こすことを、被爆国に生きるわたしたちは経験してきました。日本の司教団は戦後50年にあたって、強い決意のうちに宣言しました。
「核兵器の破壊的な力を体験したわたしたちには、その貴重な証人として、核兵器の廃絶を訴え続けていかなければならない責任があります」(「平和への決意 戦後五十年にあたって」)。核兵器廃絶に向けた取り組みは、広島・長崎と米国の司教たちとのパートナーシップによるネットワークなどにおいて広がりを見せています。今回の受賞が、核兵器のない世界に向けた希望の灯となるように祈るとともに、世界と日本政府がこの「時のしるし」を深く心に留め、一刻も早く核兵器禁止条約の署名・批准に向けて行動することを強く求めます。
真の平和とは
聖書が語る「平和(シャローム)」は、もともと「欠けたところのない状態」という意味をもつことばです。その意味で、平和は、単に戦争や争いがない状態なのではなく、この世界が神の前に欠けるところのない状態、すなわち神がきわめてよいものとして造られたこの世界のすべてが、それぞれ尊重され、調和のうちにある状態のことだといえるでしょう。ですから、平和のために働こうとするとき、わたしたち自身の神との関係、人々との関係、自然環境との関係を振り返り、神の前に望ましい関係であろうと回心し、対話することなしには前に進めません。平和とは、核兵器や武力の均衡によってもたらされるものではないのです。希望をともにして歩む
今年、カトリック教会は聖年を祝っています。これは、旧約聖書のレビ記(25章10節参照)にある「ヨベルの年」にちなんだ行事です。レビ記によるとこの年は、畑を休ませ、貧困などの理由により売却を余儀なくされた土地が返却され、雇い人となった同胞が解放され、負債が免除されたりする解放の年で、50年に一度巡ってきます。カトリック教会では、25年に一度聖年を実施し、神の前にすべての人が尊い存在であることを再確認し、権利を侵害されているならばその状態を解消し、搾取されているならばそれを返済し、負債から解放されるよう働きかけています。まさに、欠けてしまった状態から、本来の状態に戻す、平和を実現するための年といえるでしょう。前教皇フランシスコは、今年の聖年のテーマを「希望の巡礼者」とし、「聖年が、すべての人にとって、希望を取り戻す機会となりますように」と招いています。
また、新教皇レオ十四世は最初の祝福の際、「あなたがたに平和があるように……。この平和のあいさつが皆さんの心に入りますように。皆さんの家庭に、どこにいたとしてもすべての人に、すべての民族に、すべての地に届きますように。あなたがたに平和があるように」と呼びかけられました。
平和を望むすべての皆様、若者の皆様、この80年の間、幾世代にもわたって受け継がれてきた平和への歩みを自らのものとし、希望を携え、平和を紡ぐ旅をともに歩み続けてまいりましょう。
教皇フランシスコは2019年に「すべてのいのちを守るため」をテーマとして来日し、多くのメッセージを残してくださいました。これにこたえ、実際的な行動を呼びかけるために制定されたのがこの月間です。
9月1日(正教会における「被造物の保護を祈る日」)から10月4日(アシジの聖フランシスコの記念日)という期間は、元は2007年の第3回ヨーロッパエキュメニカル会議が「被造物のための期間」として提唱し、世界教会会議によって支持されたものです。被造物を大切にする世界祈願日の制定を知らせる書簡において教皇は、この世界教会会議との同調を願っています。
すべての人が手を取り合わなければ、すべてのいのちは守れません。ですから、エキュメニカルな視
点も諸宗教との協力も、ともに不可欠なのです。
2021年 すべてのいのちを守るための月間
日本カトリック司教協議会会長談話
「神の住まい、地球共同体を一新しよう」
「すべてのいのちを守るための月間」は、教皇のご意向によって2020年から実施されるはずでしたが、新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。今年は、教皇庁人間開発のための部署が発表したテーマ ―「皆のための家?神の住まいを一新する。」― をほぼそのまま紹介して会長談話とさせていただき、全教会と歩みを共にできたらと思います。>>>続きを読む