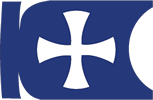みなさまお元気でしょうか。今回から、私の紋章に用いた聖句についての説明を始めたいと思います。紋章の聖句はご存じのとおり、「まず、神の国とその義をもとめよ」(マタイ6・33)です。
「まず」とは「何はさておき」、あるいは、「とりあえず」という意味です。それはマタイ6章の25節から34節を読めばわかります。つまり、「思い煩うな」ということです。「だから、言っておく。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また体のことで何を着ようかと思い煩うな」(25節)と諭すイエスは、「あなたがたの天の父は、これらのものがみな、あなたがたに必要なことをご存じである」(32節)、と天の父を心から信頼するように諭しています。
ところで、「思い煩い」の原因は何でしょうか。それは、大きな問題を抱えている場合はもちろんですが、平時の場合、情報量の多さではないでしょうか。普通私たちは、一日の初めに、その日になすべきことを思い浮かべ、優先順位をつけて、実行に移していきます。ただ、何をしたらいいのか、何を優先したらいいのか迷うことがあります。そんな時、私たちは天の父に心を向けるのです。つまり専心して祈るのです。そうすると、忘れていたことも思い出し、懸念していた事柄が好転することがあります。わたしはよくそのことを体験しています。
「神の国」を求めるとは、「人間の国」に住んでいながら、その中に神の意思を浸透させることです。福音書の中には、「神の国」(「天の国」も同義語として理解できる)について、断片的にしか語られていませんが、その特徴を列挙してみましょう。まず、それは、「神が支配している状態」あるいは「神がともにいる状態」を指します。具体的には、「愛」「正義」「平和」「真理」が充満している状態です。これらの徳目をこの世に実現させた方は、もちろんイエス・キリストです。従って、「神の国を求める」とは、イエス・キリストを追求すること、と言い直してもかまいません。
つぎに「神の国」はいのちを持っていて、成長し、完成するものです。福音書は「からし種」や「パン種」の比喩を使って説明しています。(マタイ13・31~参照)「いのち」の特徴は、小さい状態から大きくなる、ことですが、下手をすると萎んだり、亡くなったりすることです。従って私たちは、この命を大事に育てなければなりません。「人間の国」は人間の安全、安心を外面的に追求する国ですが、残念ながら、サタン(神に反抗する力)に牛耳られているため、(マタイ4・8~9参照)滅亡という憂き目に遭うことになります。
(鹿児島カトリック教区報2019年2月号から転載)