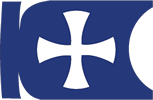教区の皆さま、お元気でしょうか。
今回は「世界宣教の日」(10月19日)に、異邦人への宣教師である聖パウロに学びたいと思います。
ご存じのようにパウロは、生粋のユダヤ人でありながら、復活したイエスとの劇的な出会いにより、主イエスの使徒(イエスから遣わされた人)となりました。彼は生前、イエス自身が召し出し、使徒と任命したペトロを頭とする12使徒とは趣を異にします。パウロはユダヤ教の教師でしたが、聖霊降臨後増えていくイエスの道を歩む人(キリスト信者)たちを迫害していました。しかしその矢先に復活したイエスと出会い、キリスト教に改宗した人です。(使徒言行録9・1〜19参照)
受洗後、パウロは熱心にキリスト教を広めましたが、キリスト信者からは迫害者、ユダヤ教徒からは裏切り者との悪評が立ち、結局ユダヤ人以外の民族、すなわち異邦人を対象にした宣教活動を始めました。ペトロを頭とする使徒たちと和解して行動をともにしたのは、14年後だったようです。(ガラテヤ書2・1参照)
今回はアブラハムの子孫で、「選民」とされていたユダヤ民族の歴史にルーツを持たない、異邦人への宣教に当たったパウロの話の4つのポイントを取り上げてみたいと思います。
なぜなら、われわれ日本人はユダヤの歴史にルーツを持たない民族の一つ、つまり異邦人だからです。
①パウロは、創世記に描かれている人祖アダムの罪に注目します。
つまり、人祖の罪とは「神の意思への不従順である」と指摘します。その前に人類の罪として、次のような論理を展開します。
「不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して、神は怒りを現されます。(中略)世界が造られたときから、目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。従って、彼らには弁解の余地がありません。なぜなら、神を知りながら、神としてあがめることも感謝することもせず、かえって、むなしい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。」(ローマ書1・18〜21参照)
この人類の罪を消すために「イエスは神の意思への従順」を実行することによって、人類は神と和解し、幸福を享受するという論考になります。
②接ぎ木のたとえ。パウロは接ぎ木の例を用いて、次のように言います。
「ある枝が折り取られ、野生のオリーブであるあなたが、その代わりに接ぎ木され、根から豊かな養分を受けるようになったからといって、折り取られた枝に対して、誇ってはなりません。誇ったところで、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです」(ローマ書11・17〜18)
このたとえは、イエスが話した「ぶどうの木のたとえ話」(ヨハネ福音・1〜17参照)の主旨と同じですが、折られた枝は異邦人だけではなく、キリストを受け入れていないユダヤ人のことを指していると思われます。私たち日本人は、完全にキリストという幹に接ぎ木されたものであり、その幹から霊的養分を、ご聖体を通していただいていると言えます。
③パウロは言います。
「あなたがたは皆、信仰により、キリスト・イエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けて、キリストに結ばれたあなたがたは皆、キリストを着ているからです。そこではもはや、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません。あなたがたは皆、キリスト・イエスにおいて一つだからです。」(ガラテヤ書3・26〜28)
このパウロの言葉は、現代社会の大きな課題である移民問題の解決の糸口になると思います。現在、日本教会は、多国籍・多文化信者の教会となっています。キリストに結ばれた信者がキリストを着る者とは、中身は違えどもみながキリストという唯一のユニホームを着けている、ということではないでしょうか。
自分たちの文化や価値観は保ちながら、キリストがめざす「神の国」の建設という共通の目的を持ちたいものです。
④最後に、宣教の必要性についてパウロの主張を聞きましょう。
「信じたことのない方を、どうして呼び求められよう。聞いたことのない方を、どうして信じられよう。また、宣べ伝える人がなければ、どうして聞くことができよう。遣わされないで、どうして宣べ伝えることができよう。」(ローマ書10・14〜15)
それまでサウロだった彼は、洗礼を受けてから、パウロと呼ばれるようになりました(使徒言行録13・9参照)。私たちも受洗した時各自洗礼名を頂きました。新生した私たちは、パウロに倣い、福音宣教に邁進したいものです。